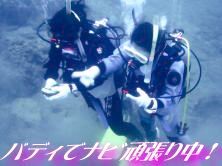こんにちは!ココモの唐沢です。
ナビ技術の目的は「引率や自分でのナビ」をイメージする方が多いですが「ガイドを依頼するダイブ」もナビ技術の活用度は高いです。分からないままついていくか、分かち合いながらついていくかは大違い。
「ナビ」と「慣れ」は別物
 「ナビ=慣れ」だと勘違いしてるダイバーに会うことが多いです。知ってるところへ行くのはナビではないです。ナビは「慣れ」ではなく「技術」です。
「ナビ=慣れ」だと勘違いしてるダイバーに会うことが多いです。知ってるところへ行くのはナビではないです。ナビは「慣れ」ではなく「技術」です。
プロでもナビが苦手な人が居ます。アドバンスなどで経験しただけで適切なトレーニングが未経験です。トレーニングといっても適切に行えばとてもシンプルです。
「SPは意味がない!」という人とは?
 本来のナビSPカリキュラムは、意味も価値も大きいですが…
本来のナビSPカリキュラムは、意味も価値も大きいですが…
「意味も価値もないコース」を受講された方は意味がなくカードをもらうだけと言われています。
そもそもスクール選択のミスです。
ナビゲーション・ダイビング
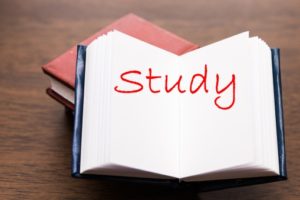 さぁ、価値あるナビを身につけるため、次のダイビングの前にまずは「ナビの知識」を確認しておきましょう。
さぁ、価値あるナビを身につけるため、次のダイビングの前にまずは「ナビの知識」を確認しておきましょう。
現実的な解説は改めて指導者さんからあるでしょう。
ナビの効果とは?
透明度が( )mと視界が良いとは言えない海でのダイビングでは一定のナビスキルが役立つ。
《詳細》
2~3
ナビゲーション・テクニックによる効果
- 心配や当惑が減る。
- 最短距離を進め、長距離移動が不要。
- 効率の良いルートで潜水計画ができる。
- チームやバディとはぐれない。
- タンクのガスを浪費しない。
《詳細を隠す》
距離測定方法は?
水中での距離は( )種類ありますがそのうち実習で主に使う次の2種類とは?
《詳細》
5実習では主に次の2種類で、約30mを泳ぐことで計測してみます。
- キックサイクル
- 左右の足それぞれがひと蹴りで1サイクル
(どちらかの足が同じ位置に戻ると1サイクル)- 練習用で、現実のナビではほとんど使わない。
- 経過時間
- 通常のリラックスした水中遊泳の速度で泳ぐ
(ナビに集中すると多くの人が速くなる)- 実習ではキック数に気が取られるが、現実のナビの主な要素。
《詳細を隠す》
ナチュラルナビゲーション
ナビゲーションに役立つ自然環境(人為的なものを含む)の5要素とは?
-
- 水中の形状や構成物(地質など)
- リーフ、チャネル(水路)、斜面
- 防波堤、テトラポット
- 岩、砂、泥、ゴミなど
例 砂紋=リップルマークは垂直に泳げば( )、間隔が狭くなれば水深は( )、広くなれば( )ことが多い。
《詳細》
沖か岸、浅く、深い《詳細を隠す》
- 動植物
- 植物の種類
- 一般にそれぞれ特定の( )で生息している
《詳細》
水深《詳細を隠す》
- ウミウチワは流れに対して、( )に生息している
《詳細》
垂直《詳細を隠す》
- カシパンウニ(タコノマクラ)は(生きていれば)岸に( )に並ぶ
《詳細》
平行《詳細を隠す》
- 広い砂地に魚が群れている場合、近くにリーフか棲み家がある
- ( )の多い動物はナビの参考になりにくい。
《詳細》
移動《詳細を隠す》
- 関連分野「ナチュラリスト」
- 音
- 慣れないと方位は分かりにくい
- ボートのエンジンの音
- アンカー(イカリ)や鎖の音
- 波で岩が転がる音
- 生物の音…など
- 光と影
- (例)15時を過ぎて太陽が見える方位(東西南北)は?
《詳細》
西《詳細を隠す》
- 太陽や月の角度や方向から
- 街頭の明かり
- (例)15時を過ぎて太陽が見える方位(東西南北)は?
- 水の動き
- (例)流れに対してボートは垂直?真っ直ぐ?斜め?
《詳細》
(多くの場合)真っ直ぐ《詳細を隠す》
- 波、うねり
- 潮流、潮汐、海流
- アップカレント、ダウンカレントなど
- (例)流れに対してボートは垂直?真っ直ぐ?斜め?
- 水中の形状や構成物(地質など)
- 活用できるボートの装備など
- ダイビング実施時、目安となるものは?
《詳細》
係留ブイ、ライン(ロープ)、アンカー(イカリ)など《詳細を隠す》
- 水深が分かる主な計器とは?
《詳細》
魚群探知機《詳細を隠す》
- ダイビング実施時、目安となるものは?
ナチュラル・ナビ(方位磁石に頼らない)での潜降方法とは?
- 頭と足の位置関係(フィートファースト?ヘッドファースト?)は?
《詳細》
頭が上で、足が下(フィートファースト)ヘッドファーストでは方向感覚が狂いやすい《詳細を隠す》
- 視線は?
《詳細》
進行方向を向く。できれば何らかの目標物を定めながら。《詳細を隠す》
- メリット
- ヴァーティゴ(ひどいめまい)を感じにくい
- 方向感覚を失いにくい
- バディでの応用は一方が水面で進行方向を維持し、もう一方がバディを頼りに潜降潜降し水中で出来れば目標物を併用し進行方向を確定する。
コンパスの各部の名称と持ち方
進行方向を向いて、自分の身体の向きと、コンパスの( )の向きが同じになるようにする。
《詳細》
ラバーライン次の様に表現されることもある
ナビゲーションでコンパスを使用する際、正確な方位をキープするには、自分の身体の中心線とラバーラインが一直線になる状態を維持する。
《詳細を隠す》
多くの市販アナログコンパスでは
-
常に自分の進行方向を指すもの:( )
《詳細》
ラバーライン《詳細を隠す》
-
常に北を指すもの:( )
《詳細》
コンパスの針《詳細を隠す》
コンパスを使った反転(Uターン)
直線移動後、逆方向を向くには(反転、Uターン)、最初の進行方向から針が( )度変進するように向きを変える。
《詳細》
180マニュアルによって次の違いがある
- 反転時、インデックスマーカー(ベゼル)を180度回す
- 反転時、インデックスマーカーは回さず、ポイントマーカー使用する
《詳細を隠す》
コンパスと方向感覚で、進む方向が異なる場合は?
コンパスは少し右を指し、感覚では少し左に思える場合などは、他に参考になる情報が無く、コンパスの使用方法が正しければ( )を信頼する。
《詳細》
コンパス次の様な場合がある
- 行きの景色と帰りの景色の見え方が異なる
予防:往路で定期的に振り返って帰りの景色を確認しておく- ベゼルが身体か何かに触れて動いている
予防:ベゼルを合わせた際、数値(方角)も確認しておく- 潮の干満で深度が異なっている
予防:目標物や地形などでナビゲーションを活用する
《詳細を隠す》
コンパスの活用を上達させるには?
- 陸上で練習やリハーサルを行う
- 流れの影響や潮汐での水深の変化を考慮する
- 障害物はナビしやすいコースで迂回する
- 中層ではナビ、深度、地形などモニターする役割を決める
- 泳ぐ速度が速くならないようにする(速くなりがち)
ナビについての確認問題
ナビゲーションの要素
ナビゲーションには、その海域についての5つの要素が必要です。
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
野生の勘での方を除いて、全て暗記することから始めてください。知らないでナビをすることは、九九や四則演算を知らず算数へ挑むようなものです。
《詳細》
- コース取り(ルート)
- 目標物(地形、構成物など)
- 距離(5つのうち現実に使用するのは主に2つ)
- 方位(コンパス)
- 深さ(計画、たどればルートになる)
《詳細を隠す》
5つの距離とは?
水中で「距離」といえば次の5つのうち、主に実用として用いるのは( )と( )です。
《詳細》
時間とエアー講習では次の理由で主にキック数で計測します
- コンパクトな範囲で繰り返す
- コンパクトな範囲で精度を測る
《詳細を隠す》
- 時間
- 時計やダイコンでの計測で、通常のダイブでは1分単位
- 透明度が悪く小さく回るときは数十秒単位のこともある
- エアー
- 実際の距離を測るというより( )などコース取りを支配する
《詳細》
折り返すまでの距離《詳細を隠す》
- 実際の距離を測るというより( )などコース取りを支配する
- キックサイクル
- 実際のナビであまり使わない
- 小さな範囲で正確さを確認する練習用
- 左右の足での1 ストローク(1 往復)が1キック・サイクル
- アームスパン
- 実際のナビであまりわない
- 宝探しなど用途は限られる
- 腕を広げた幅
「ヒロ」とは?
《詳細》
尋(ひろ)
・両手を広げた長さで、通常は1尋=6尺。
・主に水深を意味し、水底へ届く釣糸の長さを計測する目安。
・紐を両手で一杯に広げて紐を送る動作を繰り返す1回の長さ。
・1尋を約1.818mやを約1.515mとするところがある。《詳細を隠す》
- メジャー・ロープ
- 実際のナビで用いることはほぼ無い
- ナビの練習の距離を確認するなどの為の道具
?ナビゲーションの為の準備
何はともあれ…楽しく!ナビができように効率的な練習をすることです。
目標物の確認
- 情報源
- コンパスを使わないで直角に曲がる方法
- 曲がるポイントまで一直線に泳ぎ、進行方向を向いたまま停止する。
- 曲がろうとする方向が左なら左手を、右なら右手を( )に伸ばします。
《詳細》
曲がろうとする方向が左なら左手を、右なら右手を真横に伸ばします。《詳細を隠す》
- 伸ばした手の先にあるものを確認し、体全体をそちらに向けます。
ナビゲーションの4パターン
水中でのコース取り(ルート)は、複雑に考えず、基本パターンを( )と、よりナビゲーションが容易になります。
《詳細》
《詳細を隠す》
- 直線(曲線)の往復
- 方角を決め直線的に泳ぎ、方向転換して逆にたどる
- 直線の方角だけでなく、曲線的にリーフ。ウォールや水深をたどる
- 進行方向に交差する流れでずれを防ぐのにナチュラルナビテクニックを併用する
- 正方形、長方形、平行四辺形
- 正方形や長方形はコンパスを使わなくても90°に曲がれるので便利
- 2つの四角形を組み合わせることで多くの地形に当てはめられる
- 平行四辺形は方位を2つ(とその逆)使うだけのシンプルなナビ(直線往復の応用)
- 三角形
- 主に練習やゲーム用で一般にはあまり用いられない
- 応用トレーニングとしての活用が可能
- 円形
- 正確な円を描いて泳ぐのはほとんど不可能
- 主にリールやロープを使用した水中サーチで用いる
- 関連内容「サーチ&リカバリー」
水中パターン活用の注意点
- バディでルートを決めると同時に決まる潜水計画(エアー、深さ、時間)。
- 実際にパターンを書いてみる。スレート、ガムテープなどで水中へもっていく。
- ダイビング中覚えやすいシンプルなパターンでルート決めをする。
- ルート決めにナビの5つの要素((5つの要素))を盛り込む。
《詳細》
- コース取り(ルート)
- 目標物(地形、構成物など)
- 距離(5つのうち主に2つ)
- 方位(コンパス)
- 深さ(計画、たどればルートになる)
《詳細を隠す》
- バディでナビとパターンの主導権(責任者)を決めておく。
- ナビを失敗する要素と対策を考察してバディで確認しておく。
水中用コンパス
コンパスナビをする際の確認事項。陸上用とは針の動き、ベゼル等が異なります。
- 液体封入式
- 耐水圧用に磁針を液体を封入し動きがゆっくり滑らか。
- 動きのよい磁針
- 完全に水平でなくても、正確に方位を示す。
- 方位表示
- 方位は( )ではなく( )で表示されている。
《詳細》
方位は東西南北(NEWS)ではなく数字で表示されている。《詳細を隠す》
- 方位は( )ではなく( )で表示されている。
- 水中でも見やすい
- 夜や暗い場所でも読める蓄光式。
- ラバー・ライン、横窓、ベゼル
- ラバーライン:コンパスを真っすぐに保持できる
- ダイレクト・サイト(のぞき窓、横窓):目標物に重ねて方位がよめる
- ベゼル:( )マーカーや( )マーカーが付いていて方位を設定できる
《詳細》
インデックス、ポイント《詳細を隠す》
電子コンパス
様々なタイプがあるので、それぞれメーカーの取り扱い説明書を参照ください。
ただし、実際のナビゲーションで現在のデジタルコンパスで満足な機能を有するものはあまりない。
筆者はデジタルコンパスを用いているプロを知らない。
コンパス使用法
保持のしかた
- まず( )を合わす(体の真正面で真っすぐに持つ)。
《詳細》
ラバー・ライン《詳細を隠す》
- リスト・コンパス(左手装着時)
- 右手をまっすぐ前に出し肘の手前を左出てつかむ。
- コンパスが身体の真正面で、体に対して( )になるように持つ。
《詳細》
直角(垂直)《詳細を隠す》
- コンソールコンパス
- 体の( )に位置するよう( )でコンソールを持つ。
《詳細》
中心、両手《詳細を隠す》
- ( )や両脇を閉じるか( )を伸ばす。
《詳細》
両肘、両手《詳細を隠す》
- 体の( )に位置するよう( )でコンソールを持つ。
新たなナビゲーション器材
このコラム作成時には、水中で使用できる測位システム((GPS 信号は弱すぎて水中では簡単に受信できません))はありませんが、現在開発段階にあります。
コンパスを使って泳ぐ
- 正しくコンパスを持つ
- 正面
- 水平
- ベゼル(インデックスマーカー、ポイントマーカー)と針の位置など
- 次のどちらかで( )を優先する(コンパスをメインとしない)
《詳細》
ナチュラルナビ《詳細を隠す》
- 目標物をコンパス越しに見るようにしながら泳ぐ
- 真上から見下ろしそのまま顔をあげ、正面に向かって泳ぐ
コンパスのセッティングと直進
- 進行方向を向く
- 北を示す針に( )を合わす
《詳細》
インデックスマーカー《詳細を隠す》
- インデックスマーカーに針がとどまる状態で正面にある( )を見定める
《詳細》
目標物《詳細を隠す》
- 正面に有るものまで泳ぎつつ、コンパスを確認し、次に正面に見える目標物を設定する。
- 泳いでいてマーカーから針が外れると違う方に向いている
- 透明度が低い場合は正面に有るものよりコンパスに頼ることがある
逆方向(帰りの方向)のセット
- 方法1
- 折り返し地点で止まる。
- インデックス―マーカーを180°回転させる。
- 磁針がインデックス・マーカーに入るように身体の向きを変える。
- 往路と同じように(実際は逆向き)ナチュラルを併用して泳ぐ。
- 透明度が低い場合は同様にコンパスに頼ることがある。
- 往路で見たものが復路でも見れるはず。
- 方法2
- 折り返し地点で止まる。
- インデックスマーカーはそのままでコンパスにより次のどちらかで反転する。
- 針が( )を差すように身体の向きを変える。
《詳細》
ポイントマーカー《詳細を隠す》
- インデックスマーカーに磁針の( )が入る様に身体の向きを変える。
《詳細》
南側《詳細を隠す》
- 針が( )を差すように身体の向きを変える。
- 往路と同じように(実際は逆向き)ナチュラルを併用して泳ぐ。
- 透明度が低い場合は同様にコンパスに頼ることがある。
- 往路で見たものが復路でも見れるはず。
正方形や長方形のナビゲーション
- 方法1
- 曲がり角で止まる。
- インデックス―マーカーを( )度回転させる。
《詳細》
90《詳細を隠す》
- 磁針がインデックス・マーカーに入るように身体の向きを変える。
- 再びナチュラルを併用して泳ぐ。
- 透明度が低い場合は同様にコンパスに頼ることがある。。
- 方法2
- 曲がり角で止まる。
- インデックスマーカーはそのままでコンパスにより次のどちらかで曲がる。
- インデックスマーカーに磁針の東や西が入る様に身体の向きを変える。
- 再びナチュラルを併用して泳ぐ。
- 透明度が低い場合は同様にコンパスに頼ることがある。
三角形のナビゲーション
手順は正方形や長方形の場合と同様で、曲がる際にインデックスマーカーを( )度回転させる。(コンパスによって異なることがある。)
《詳細》
120《詳細を隠す》
六角形のナビゲーション
手順は正方形や長方形の場合と同様で、曲がる際にインデックスマーカーを( )度回転させる。(コンパスによって異なることがある。)
《詳細》
60《詳細を隠す》
( )ターンすると元の位置に戻る。
《詳細》
5 回《詳細を隠す》
コンパスを使いこなすヒント
視界にもよるが、大前提はナチュラル・ナビゲーションの補助としてコンパスを使う。
- コンパスを信頼する
- 使用法さえ合っていて、壊れてなければ感覚よりコンパスを信じる。
- コンパスが間違っていると思うことがあるが、ダイバーの方向感覚が失われてることが多い。
- コンパスは( )の基本的法則で、方向感覚は天気予想のような( )の場合が多い。
《詳細》
物理、直観《詳細を隠す》
- 感覚の方が正しいことがあるとすれば、コンパスナビゲーションでなくナチュラルとしての何らかの根拠がある場合でしょう。
![080809-08[1]](http://pro.cocomo.jp/wp-content/uploads/2016/04/080809-081.jpg) 陸上での練習
陸上での練習
- コンパスには固有の特性(デザイン、昨日、動きなど)があるので、同じコンパスで慣れることです。
- 慣れるには水中でなくとも陸上で練習できます。
- 流れの影響を計算に入れる
- 潮流やウネリなどの水の動きによってコースから外れることがある。
- ナチュラル・ナビゲーションで( )を活用すると水流の影響を防げる。
《詳細》
目標物《詳細を隠す》
- 障害物を迂回する
- ( )度のターンを組み合わせる。
《詳細》
90《詳細を隠す》
- 障害物が大きい場合は、障害物に指標を設置し、障害物に沿ってコースをアレンジする。
- ( )度のターンを組み合わせる。
- PADIスクーバセクスタント
やナビファインダーを活用する
- 不規則なコースのマッピングが可能になります。
- 活用を続けることで、そろばんに慣れた方の暗算の様に、視覚的にナビの全体像をとらえられるようになります。
- ナビゲ-ション用器材を使う
- コンパス・ボード、マップを書いたスレートなど
- 限界を知っておく
- 長距離をカバーする必要がある場合誤差が大きくなるので、水面移動を組み合わせる。
- 不明なまま突き進まず可能であれば、定期的に水面に出て位置を確認する。
- 技量に合わせた範囲をナビゲーションする。
- ゆっくりと泳ぐ
- リラックスし、コンパス以外に、水深、目標物などに注意を向ける。
ここまでがナビ全体像の1/3です
①はナビゲーションの基本練習で、一般のスポットで十分なナビをする技術ではありません。ナビゲーションのテクニックの全体像は②と③で完結します。あとはその応用として幅を広げることになります。
ナビSP②
- ナビSP①が自分主体のナビであるのに対して、②では既知の地形やマップに合わせたコース取りができるようになります。
- ナビSP①のテクニックを踏まえ、パターンを様々組合すことで海域に合わせたナビゲーションができるようになります。
ナビSP③
- ナビSP②が既知の海域やコースであるのに対して、③では未知のスポットで自由自在に移動し、元に戻れるようになります。
- ナビSP①と②のテクニックを踏まえ、未知の海域で移動しながら、起点と自分の居る位置を把握しながらナビゲーションができるようになります。
![0602-35[1]](http://pro.cocomo.jp/wp-content/uploads/2016/04/0602-351.jpg) セクスタントは下記、またはこちらからご購入いただけます。
セクスタントは下記、またはこちらからご購入いただけます。